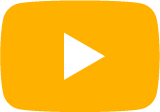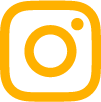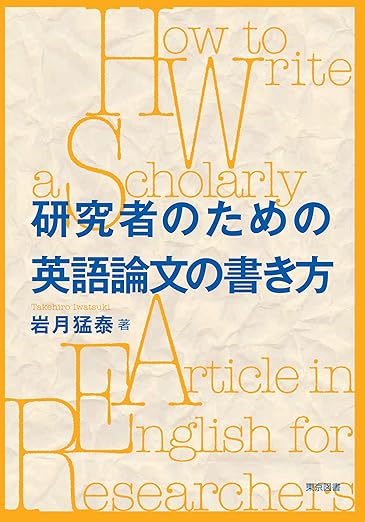博士課程は得なのか?進学を迷う人へ伝えたい“5つの利点”と現実

博士課程って本当に行く価値があるの?
お金や就職の不安が先に立つ一方で、進学でしか得られない具体的な利点もあります。判断材料を事実だけで整理します。
まず、教員の道に近づくこと。大学でのキャリアは段階的に上がっていきます(assistant professor/associate professor/professor。日本では助教・准教授・教授)。多くのポジションで博士号は前提条件となり、取得は出発点になります。
次に、やる気の高い仲間と出会えること。国内外から集まる学生の目的意識は強く、スポーツ心理・運動学の領域でも、研究者、大学教員、カウンセラー、プロスポーツチームのデータアナリストなど、多様な進路をめざす人たちと切磋琢磨できます。共同研究の話が生まれるなど、学びが継続する関係も築かれます。
三つ目は、経済面の現実的な利点。アメリカでは学費免除と給与が組み合わさる制度が一般的で、仕事を得られれば学費負担を抑えつつ生活を回せます。ルームシェアなどを活用すれば、少額でも貯金ができたという体験も示されています。
四つ目は、研究論文の書き方を体系的に学べること。世界的に引用の多い研究者の理論や書籍で学び、厳密な指導のもとで執筆技法を磨きます。ドイツ出身でアメリカ在住の指導教員からの細かな指導など、国際的な視点も得られます。成果を「形に残す」力は、研究職に限らず重要です。
五つ目は、専門知識の厚み。運動学を主専攻、心理学をマイナーとして深めるなど、科目数が多いアメリカのカリキュラムでは、複数の教員から重層的に学べます。他国では授業中心でない博士課程もある中、授業を通じて土台を厚くする設計が特徴です。
ボーナスとして知っておきたいのは、環境の「社会人寄り」な性質。アメリカの大学院には30代・40代の学生も珍しくなく、給与を得ながら学ぶため、働く感覚に近い日常になります。たとえば博士課程を31歳で修了した例と、同時期に45歳で修了した例が並ぶなど、年齢は大きな制約になりません。期間は3年、5年、6年と幅があり、分野や進め方で変わります。進学の是非は、こうした現実的な利点と自分の将来像を照らし合わせて判断するのが近道です。
教員への近道、仲間と機会、学費面の工夫、論文作法、専門性の厚み。さらに社会人寄りの環境。必要なのは「自分に必要な利点がどれか」を見極めることです。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

卒論は”小さく、確実に”:迷わず進める実践ガイド