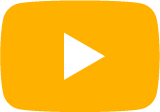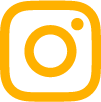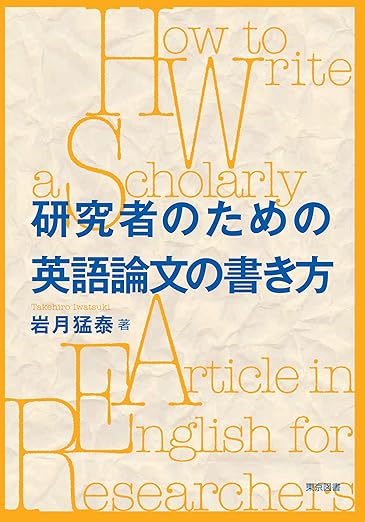英語力を底上げする5つの勉強法――文法の土台から「話す」実戦まで

「英語を頑張っているのに伸びを実感できない」そんな壁はありませんか?
勉強の順番と負荷のかけ方を具体化し、日々の学習にそのまま落とし込める方法を整理します。
一つ目のポイントは「文法と読む力の土台づくり」です。中学レベルの文法すら曖昧だと、文の構造が捉えられずリスニングも伸びにくいです。まずは手頃な参考書で基本文法とやさしい語彙を入れ、読む力を確保します。受験経験がなくても、文法の筋道を通せば次の段階に進めます。
二つ目は「聞き流しではなく、聞き取る練習」です。ただ流すだけでは理解が積み上がりません。フレンズのようなドラマやTOEFL教材など、音声を使って「何を聞き落としたか」を自覚的に拾います。重要なのは、理解しようと集中する“疲れる”聴き方を日課にすることです。移動中は流すだけでも構いませんが、机に向かう時間は必ず「聞き取る」に切り替えます。
三つ目は「とにかく話す」ことです。オンライン英会話などを使い、英語で30分話す負荷を定期的にかけます。話す行為は同時に高度なリスニング練習にもなります。聞く<聞き取る<話すの順で認知負荷が上がり、理解していないと口から出ないため、語彙・文法・聴解の穴が可視化されます。英語での対話はストレスがかかりますが、その負荷が伸びに直結します。
四つ目は「語彙は闇雲に覚えない」ことです。単語は重要ですが、使う場面が見えないまま大量暗記すると忘れやすいです。読んで分からなかった語、聞いて取れなかった語を都度ストックして覚えるほうが定着します。模擬テストや教材で遭遇した未知語を優先し、理解のボトルネックを順に外していきます。
五つ目は「読む・聞く素材のレベルを段階的に上げる」ことです。4つの基礎が回り始めたら、半分以上は理解できるが少し背伸びが必要な教材に切り替えます。難しすぎる素材は継続性を損ない、易しすぎる素材は伸びを止めます。わからない表現に出会う頻度を意図的に増やし、四つ目の語彙補強に循環させます。完璧主義は不要で、全体の要旨が掴めれば十分です。日本語でもすべての語を逐語的に把握しているわけではありません。英語も同様に、要旨理解を積み重ねながら、徐々に精度を上げていきます。
この5手順は直線ではなく往復運動です。「文法→リスニング→スピーキングで露呈した弱点を語彙で補い、素材の難度を一段上げる」という循環を回すことで、学習の疲労感が「手応え」に変わります。これら一連をサイクルにすると、停滞が解消しやすくなります。完璧を求めず、負荷の“心地よい疲れ”を積み上げていきましょう。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

博士課程は得なのか?進学を迷う人へ伝えたい“5つの利点”と現実