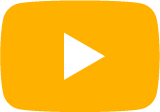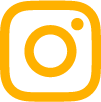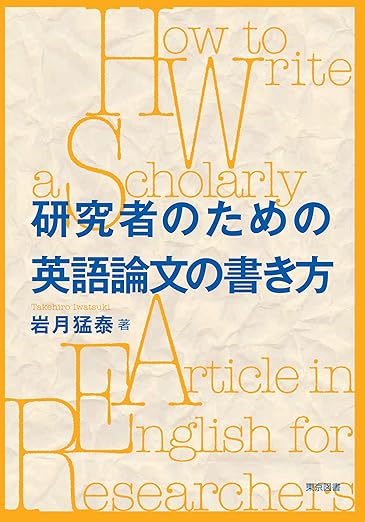大学教員を目指すには研究が好きじゃないとダメ?大学教員が語るリアルな考え方

「大学教員って研究が好きじゃないと無理ですか?」こんな悩みを抱えている人、意外と多いのではないでしょうか?教えることが好きでも、研究に不安がある場合、進むべきかどうか悩むのは自然なことです。
大学教員になるために、研究の実績は不可欠です。日本でもアメリカでも、教員として採用されるためには論文の数や内容といった“研究業績”が求められます。なぜなら、授業の上手さは定量的に評価しづらい一方で、研究業績は論文数や掲載先で客観的に示せるからです。
模擬授業などで教育スキルを直接アピールできる場もありますが、それでも研究成果がないとそもそも候補に入らないケースも少なくありません。たとえばハワイ大学のように応募者が70人を超えるポジションでは、研究実績が一つの選考基準としてまずチェックされます。
一方で、「研究がものすごく好きで仕方がない」というタイプでなくても、教員になることは可能です。実際、大学教員の中には、教育への情熱を原動力にしている人も多く存在します。教えることが好きで、大学院でティーチングを経験しながら進んでいく。そんなアプローチでも十分にやっていけるのです。
研究に苦手意識があっても、やってみることで楽しさに気づく場合もあります。特に論文の書き方や研究の進め方に慣れてくると、自分なりに工夫できるようになり、負担感は徐々に軽減されていきます。教えることがルーティンになりやすい分、研究の新しさやチャレンジ性が刺激になっているという声もあります。
重要なのは、自分に合った研究スタンスを確立することです。たとえば「毎年1〜2本の論文を書けばOK」という大学のノルマを満たせる範囲で、自分の興味ある研究だけに取り組むというスタイルでも問題ありません。むしろ、無理に全ての依頼を引き受けるのではなく、自分が本当に貢献できると感じたテーマだけに絞ることで、研究も楽しさが増します。
さらに、国際的な共同研究の依頼も定期的に届くようになれば、自分がどの分野でどんな役割を果たせるのか、という強みも明確になります。「この人と一緒に研究すれば、英語の論文が通るだろう」と世界から声がかかる存在になることもあるのです。
つまり、研究が「絶対に大好き」である必要はありません。教育への情熱があり、必要最低限の研究をこなせる覚悟があれば、十分に大学教員というキャリアは目指せます。研究が苦手だからといって進学を諦める必要はないのです。
研究に強い情熱がなくても、大学教員を目指す道はあります。重要なのは「やりたいこと」と「やらなければならないこと」のバランス。教えることが好きなら、それを中心にキャリアを築きつつ、自分に合った形で研究と向き合っていくスタンスも、立派な選択肢です。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

アメリカ博士課程でのリアルな生活: 授業・研究・就活をどう乗り切るか