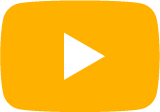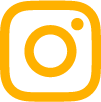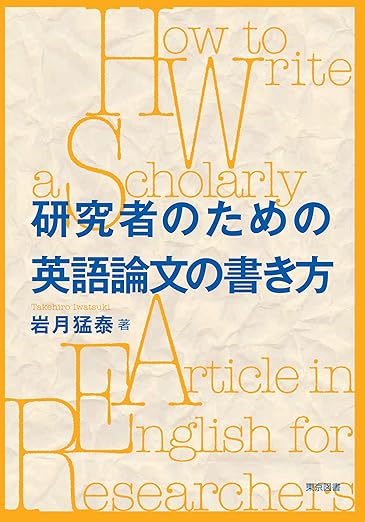アメリカ博士課程でのリアルな生活: 授業・研究・就活をどう乗り切るか

博士課程に進むって、実際どんな日々を過ごすんだろう?授業や研究だけじゃなく、生活費や働き方、就職活動まで見通しておきたい。そんなふうに考える人も多いのではないでしょうか。
アメリカの博士課程に入って最初の年は、とにかく忙しく、慣れるまで本当に大変でした。1学期目は授業を3つ取りつつ、研究アシスタントとして働きました。授業はどれも課題やプレゼンが多く、日本の大学院とは比べものにならないほど密度が高かった印象です。研究アシスタントの立場では、1年間で約500万円分の学費と生活費の支援があり、その分、研究室での業務や責任も求められました。
2学期目になると、今度は自分で授業を持つことに。週2回、90分ずつスポーツ心理学の授業を一人で教える経験は、指導スキルを磨く貴重な機会でしたが、準備や学生対応にかなりの時間を使いました。また、研究費を申請し、夏にはチェコで現地の研究機関と共同でデータ収集をする計画も進めていました。これは全てのPhD生が経験することではなく、あくまで僕個人の研究テーマや資金のチャンスがあったからこそ実現した例です。
3学期目(夏)は、そのチェコでの研究がメインになりました。滞在中は現地の大学で机を借りて研究に取り組み、チェコ人研究者とも連携してデータ収集を行いました。一方で、アメリカの博士課程は通常4年での修了を目指すため、夏も休まずオンラインで授業を履修。12月卒業だと就職活動のタイミングとずれる可能性があるため、学期の計画にも戦略が必要でした。
2年目に入っても、授業3つ、研究アシスタント業務、授業担当は継続。その頃から、論文執筆や査読対応も本格化しました。論文は査読者から修正が返ってくることも多く、提出して終わりではありません。また、この年の夏には博士課程で非常に重要な「包括試験(Comprehensive Exam)」がありました。これは博士候補として認定されるための試験で、かなりの準備が必要です。僕の場合、6月までみっちり勉強し、7月に受験して合格。ここでようやく「PhD Candidate」としての立場になりました。
3年目からは授業はなくなり、研究と論文執筆に集中する期間になりました(長いプログラムだともう少しプロセスが長くなります)。この時期、就職活動も本格化。アメリカの大学に教員として応募するため、30校以上に出願し、Zoomでの面接やオンキャンパスインタビューも経験しました。現地での発表や模擬授業の準備には多くの時間がかかり、この就活が博士論文と並行して進むのは、かなりのプレッシャーでした。
最終学期には、博士論文としてまとめる3本の実験のうち、2本はすでに投稿済み、1本は掲載済みという状態に。最後に学内でプレゼンテーションを行い、質疑応答を経て、無事に博士号を取得しました。アメリカの博士課程では、論文がすべて掲載済みでなくても提出できるケースもありました(大学や分野により異なります)。僕自身は、比較的スムーズに進められたほうかもしれません。
アメリカの博士課程は、授業・研究・指導・就職活動の全てが並行して進みます。すべての体験が共通とは限りませんが、現地で実際に学んだ人の1年を知ることで、より具体的な準備や心構えができるはずです。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

論文は全部読む必要なし。目的別・効率的な研究論文読み方