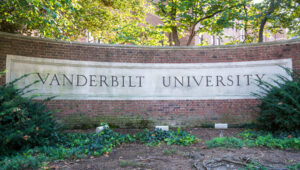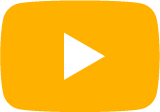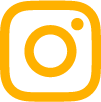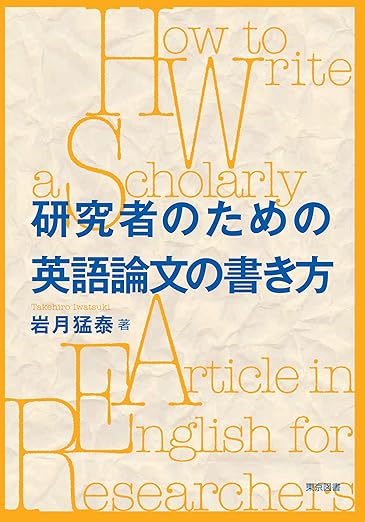論文の「考察」を通すために――5つの確認ポイントと仕上げの一手

「考察、何を書けばいいの?」と手が止まっていませんか?
結論の説得力は、考察の設計で大きく変わります。実務で役立った要点を、手順として明快にまとめます。
一つ目のポイントは、先行研究との違いを具体化することです。 自分の研究が他の研究とどこが同じで、どこが違ったのかを明示します。「ここは一致、ここは乖離」と見出しレベルで切り分けると、主張がぶれません。
二つ目のポイントは、結果を“超短く”要約してから広げることです。 考察冒頭で、伝えたい主要結果を一言で提示し、その後に解釈・理論的含意・現場での意味を展開します。段落ごとに短い要約→議論という流れを繰り返すと、読み手の負荷が下がります。
三つ目のポイントは、「分からないこと」を書くことです。 すべてを説明できる研究は多くありません。対象や条件に依存する限界を明確化し、「男性データはあるが女性は未検証」などの範囲を示します。分からない点を残すことは、誠実さと再現可能性の核になります。
四つ目のポイントは、結果の繰り返しを避けることです。 考察は「なぜその結果になったのか」を説明する場所です。同じ文章の焼き直しでは査読に耐えません。例えば米国の肥満割合を例示したなら、「なぜ高いのか」という要因仮説や関連知見に踏み込みます。
五つ目のポイントは、次に何を検証すべきかを示すことです。 将来の研究課題を具体化すると、他研究者が引用・追試しやすくなります。実際に、将来課題を明記し始めてから引用が増えたという実感も語られています(年1〜2件が目安とされる領域で増加傾向)。
仕上げとして重要なのは、「この研究はなぜ重要か」を最後に書くことです。 理論的・実務的意義を一段で言い切ると、読後の納得感が格段に高まります。重要なのは、結論の再掲ではなく価値の言語化です。
考察は「短い結果要約→解釈」「一致と乖離の切り分け」「限界と次の一歩」の三点で骨格が決まります。大事なのは、結果の説明・不確実性の明示・意義の宣言を欠かさないことです。ここまで整えば、主張は数字以上に強く伝わります。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]
【関連動画紹介】

ハワイで仕事を得たい人へ:現地の働き方・人種構成・採用事情を数字で読む