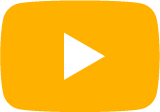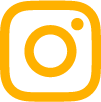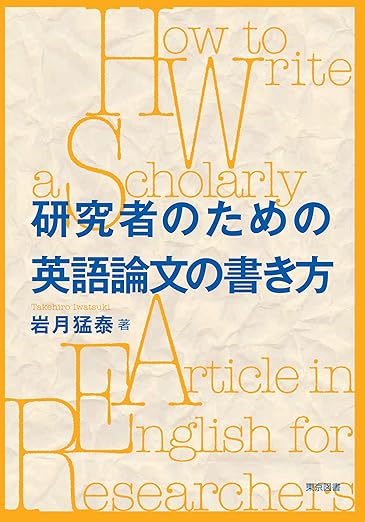卒論は”小さく、確実に”:迷わず進める実践ガイド

卒業論文、どこから手をつければいいのか、悩んでいませんか?
卒論は「小さくまとめる」ことが肝。具体的手順と注意点を、必要な事実だけで整理します。
出発点はテーマ選び。最初に自分の興味からキーワードを3つ挙げ、組み合わせて絞り込みます(例:テニス/プロ試合/サービス)。次に「何を解決するか」をはっきりさせます。研究は問題解決の営みです。小さい課題で構いませんが、解決の形が見えるテーマを選ぶと筋道が通ります。
先行研究を調べる際は、やみくもに論文を積み上げるのではなく、複数研究をまとめた総説(レビュー)を優先して読みます。そこには「何が分かっていて、何が未解決か」が整理されており、自分の穴埋めポイントを見つけやすいからです。
データ収集は目的達成に必要な最小限に限定します。詰め込みすぎるほど分析は散漫になります。たとえば「プロのサービス成功率を調べる」という目的なら、成功率の測定に集中し、他指標は切り捨てます。
文章量も同様に圧縮を意識します。長さは質の証明ではありません。目的は短く明確に、説明は目的達成に不可欠な情報に限ります。
構成は定石に沿うと進めやすいです。まず抄録(約200字)。続いて序論(背景→関連研究→未解決点→本研究の必要性と目的)、方法(対象・手続き・分析法)、結果(統計結果を簡潔に数値で提示)、考察(結果が出た理由を先行研究と照合し解釈、実務的含意も簡潔に)、参考文献の順に並べます。方法は先行研究の記述を参考にしやすい領域で、設計が類似していれば書きやすくなります。結果では、たとえば男女差を検討したなら「差があった/なかった」を統計処理に基づく値とともに提示します。考察では「先行研究ではこう報告→本研究結果はこう理解できる」を2点程度に整理し、最後に目的・結果・解釈・意義を短くまとめます。
仕上げに欠かせないのが体裁です。見出し、余白、図表番号、参考文献の書式など、まず“見た瞬間に整っている”状態に。整っていないだけで印象は大きく損なわれます。
最後に重要ポイントを二つ。第一に、評価者(指導教員)へこまめに確認すること。進めてからの手戻りは負荷が高く、早期の合意が最短ルートです。第二に、終始一貫して「小さくまとめる」。データも論点も目的直結の1~2点に絞るほど、読み手にも自分にも分かりやすくなります。
テーマは小さく、目的は明確に。総説で方角を定め、最小限のデータでIMRADを整える。体裁と確認を怠らなければ、卒論は着実に形になります。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]
【関連動画紹介】

アメリカの大学院は本当に高いのか?99%の人が知らない学費無料と給与で通えるリアルな仕組み