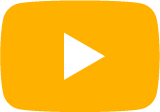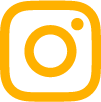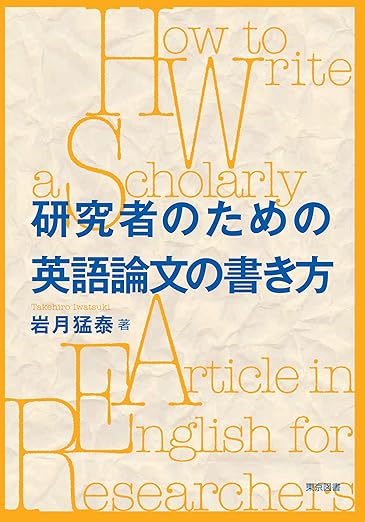論文が書けない大学生・大学院生のための英語論文掲載までの成長ステップ

研究を始めた時、「アイデアが浮かばない」「文章が書けない」と壁にぶつかった経験はありませんか?
多くの研究者が通るこの道には、段階的な成長のプロセスがあります。
研究の出発点は、まずテーマやアイデアを見つけることです。暗記中心の学習から一転して、自分で課題を設定する段階に移ると、多くの人が戸惑います。解決策は徹底的に論文を読み込み、まだ取り組まれていない領域を探すこと。これが研究の第一歩となります。
次に立ちはだかるのは「文章が書けない」という壁です。大学4年生の頃はパソコンスキルも未熟で、文章作成自体に苦労する人も少なくありません。最初は指導教員の論文を手伝いながら書き方を学び、少しずつ自分自身の論文執筆へと移行していきます。修士課程に入る頃には、日本語での論文執筆に慣れ、ようやく独力で形にできるようになります。
その後、多くの研究者が挑戦するのが英語論文です。最初の一本を書くまでには時間がかかり、表現の拙さや多くの修正を経ることになりますが、一度書き上げれば次第に慣れ、執筆のスピードも上がります。最初はレベルの高くないジャーナルに掲載されることが多いものの、経験を積むにつれて、よりインパクトのある学術誌へと挑戦できるようになります。
さらに進むと、査読の依頼が届くようになります。他者の研究を評価する経験は、自分の論文執筆スキルを磨く格好の学びとなります。博士課程の途中から査読を始める人も多く、これを通じて「研究者として一段上に上がった」と実感する瞬間が訪れます。
論文が増えてくると、国内外の研究者から共同研究の誘いも届きます。異なる国の研究者と協力しながら執筆を進めることで、1本あたりの負担が軽減されると同時に、研究の幅も大きく広がります。数年のうちに複数の論文を同時進行で進められるようになり、研究コミュニティにおける存在感も強まっていきます。
こうした積み重ねの結果、英語論文が次々と受理されるようになり、年間で複数本の掲載が実現する研究者もいます。執筆や査読を通じて蓄積した知識は、数年後に振り返ると明らかな成長として実感できるのです。
研究の道は一足飛びではなく、誰もが同じように壁を越えながら進んでいきます。重要なのは「自分がどの段階にいるか」を把握し、一歩ずつ積み上げていくことです。
研究の成長は段階的で、最初の苦労も後に必ず力となります。焦らず積み重ねていくことが、論文執筆力を確実に伸ばす近道です。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]
【関連動画紹介】

大学教授への道:卒論から博士号・ポスドクまでの完全ロードマップ