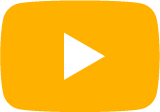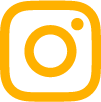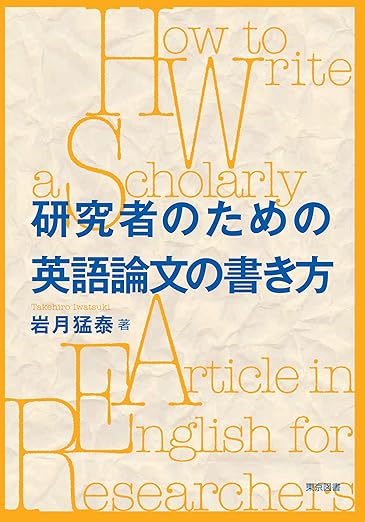米大学院の費用はどこで膨らむ?――公立・私立の違いと現実的な節約策

留学費用、結局いくら必要なの?
内訳が曖昧だと準備の手が止まってしまいますよね。公立・私立の違いと具体額の目安、抑え方を整理します。
一つ目のポイントは、費用の三本柱(授業料・保険・ノンレジデントフィー)を分けて把握することです。例として、ある公立大学院の学期明細では授業料26,401ドル、保険901ドル、州外者向けのノンレジデントフィーが約7,000ドルと示されています。細かな諸費用(インターナショナルフィー145ドル、施設利用関連など)も加わり、合計は学期あたり約1万1,000ドルという水準でした(当時の例)。
二つ目のポイントは、「公立=安い」の思い込みを外すことです。公立は州内居住者が優遇されますが、留学生は基本的に州外扱いのためノンレジデントフィーが上乗せされます。結果として、公立でも学費総額が下がらないケースが普通にあります。
三つ目は、為替前提での総額試算です。学期あたり約1万1,000ドルとすると、修士2年の学費・学籍関連だけで約440万円(1ドル=100円)〜約660万円(150円)のレンジ感になります。生活費はルームシェアでも月15万円程度を見込む例があり、帰省や外食などを含めると、2年間の総額は1,000万〜1,500万円を想定するのが現実的とされています。なお、例に挙げた公立大学の明細は2016年時点のもので、近年は上振れしているケースもあります。
四つ目は、私立の単位制の読み解きです。例として1単位1,178ドル、1科目3単位、フルタイムは9単位という前提では、1科目あたりの授業料は約3,534ドル、学期あたりは約1万602ドルになります。修了要件36単位なら、学費合計は約630万円(100円換算の試算)という見積りも示されています。ここに保険や諸費用が別途加わります。
五つ目は、費用を下げる具体策です。代表例は奨学金の獲得(フルブライト等、種類は50〜100以上)と、大学院での職(ティーチング/リサーチ・アシスタント等)です。実例として、大学院アシスタント業務により授業料免除(各種ウェイバー)が適用され、さらに9か月で1万7,000ドル(約250万円相当)の給与に加え、夏期に約150万円の収入が得られたケースがあります。学部側からのファイナンシャルエイドが出ることもあり、結果として学費の自己負担が発生しないパターンも現実にあります。
重要なのは、最初に「内訳→為替前提→期間」で総額を固め、同時に免除・収入の当たりを付ける設計です。 公立・私立の看板で判断せず、ノンレジデント加算や単位要件を数字で確認し、奨学金とアシスタント職の募集要項を早期に並走チェックすることが、予算の不確実性を大きく下げます。
費用は「どこで」「どれだけ」増えるかを数字で掴めば対策が立ちます。「内訳と為替の前提を明確化し、奨学金とアシスタント職で負担を削る」この順番が要です。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

付箋を使った論文執筆システム――大きな課題を小さく分解する思考法