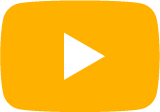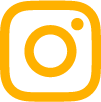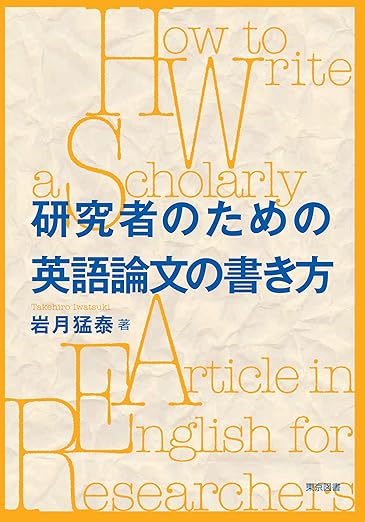留学で直面した“しんどさ”――英語・文化・ビザの壁をどう乗り越えるか

「海外で学びたい。でも実際の大変さが見えない」そんな不安はありませんか?
現地で直面した具体的な“しんどさ”を、事実ベースで整理します。
一つ目のポイントは「英語運用の壁は生活の細部で露呈する」ことです。24歳で渡米した当初、サンドイッチ店では質問が理解できず、毎回同じメニューでやり過ごす場面がありました。わからないまま会話を進めてほしいと感じるほど、何がわからないかすら掴めない局面が続くのです。
二つ目のポイントは「名前問題の実務対応」です。スターバックスで名前を聞かれた際、”Takehiro”は長く伝わりづらいため、”Hiro”でも綴りを頻繁に聞き返されます。そこで実務上は“Mike”と名乗ることで受け渡しをスムーズにしました。小さな最適化ですが、日常のストレスを確実に減らします。
三つ目のポイントは「学業負荷の非対称」です。英語の教科書1ページに1時間かかると、10ページで10時間、同様の授業が4つなら40時間が必要です。周囲の学生が短時間で課題を終える一方で、自分は何倍もの時間を投じる現実があります。重要なのは、同じ課題でも処理時間が根本的に違うと認識することです。
四つ目のポイントは「文化差の直撃」です。集合時間の感覚は国や地域で異なり、約1時間の遅刻が起きることもあります。食文化もズレます。生魚が苦手な人が多く、寿司は「カリフォルニアロール」のように別の形で受容される場合があります。重要なのは、正解を押し付けず、相手側の“普通”を前提に調整する姿勢です。
五つ目のポイントは「ビザと就労の不確実性」です。ビザの到着が遅れて内定が消える事態も実際に起こりました。働くには政府発行の許可が必要で、弁護士を雇う場面もあり、費用や手続きの負担が重くのしかかります。スケジュールは自分で決められず、外的要因に左右されます。
最後に「友人づくりの難しさ」です。言語の壁で会話の厚みが出にくく、共通点の総量が少ないため関係が深まりづらいことがあります。出身地が偶然一致するなど、共通点を丁寧に拾うことで距離は縮まりますが、同国コミュニティと比べれば時間がかかります。
これらは誇張のない実体験の断面です。重要なのは、課題を“個人の能力不足”と決めつけず、構造的なハードルとして捉えることです。そうすることで、対処の糸口が見え、必要な時間・手段・助けを冷静に見積もれます。
英語、文化、ビザ、交友関係など、留学の壁は生活全域に及びます。数字と事実で直視し、現実的な手当てを積み上げることが、消耗を減らし前に進む最短路になります。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]
【関連動画紹介】

研究者になる近道は?学部から博士後までの実践ステップ7つ