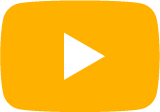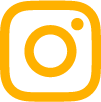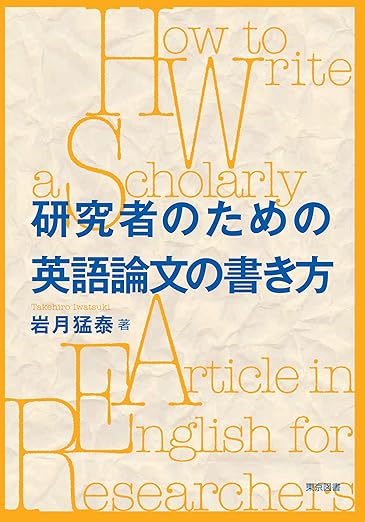【日米比較】博士課程はどう違うのか:学位取得から学費・指導まで徹底解説

博士課程って、国によって何がどう違うの?
費用や指導、試験の中身まで、実際の体験と具体的な数字で「日本」と「アメリカ」の違いを整理します。
学位取得までの道筋はまず大きく異なります。日本では博士論文の基盤として1〜3本の論文掲載(うち1本は英語必須とする大学も)が重視され、途中で満期退学という選択肢もあります。一方アメリカでは最初の約2年間で多くの授業を履修し、その後に包括試験(Comprehensive Exam)を受けます。試験は72時間で6〜7問に回答する形式などがあり、合格すると「ABD(All But Dissertation)」、つまり論文以外を終えたステータスになります。実例として、研究法・統計・専門科目を積み上げて授業ベースで55単位、博士論文単位を含め合計67単位、GPA3.75というケースもあります。
指導体制と距離感も対照的です。日本は教員と日常的に顔を合わせる近さがあり、アメリカはよりアカデミックに距離が保たれる傾向。ただしいずれも指導の質は教員次第です。生活と費用面では差がさらに明確。日本は年間40〜80万円規模の学費を自己負担する人が多く、TAの手当も学費全額や生活費を賄う水準ではない例が一般的です。アメリカの博士課程は学費が年350〜700万円と高額ながら、RA/TAでの学費免除と給与が主流で、自己負担は稀という実感値。給与の目安は年200〜600万円程度というレンジが示され、月28万円程度の支給で家賃9万円(ルームシェアで折半)、食費5万円、通信光熱費を差し引き、毎月5万円ほど貯金できた具体例もあります。
研究費・学会参加は、所属や大学の研究力に依存しますが、年1〜2回の学会に大学や学部の支援で参加できるケースが多く、国内移動で費用を抑え、国際学会や遠方(ボストン、カナダ)は航空券を含め20〜30万円規模の支出になることも。キャリアの見られ方も違い、アメリカでは博士課程は「学生でありつつ職務責任も負う」存在として認識され、大学教員・研究者はもちろん、分野によっては企業研究職の道も一般的です(例:計算機系では初任年収が非常に高い事例がある)。
授業中心→包括試験→ABD→論文という流れ、学費免除と給与、指導距離感。これらを理解すると、博士課程の選択はぐっと具体的になります。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]
【関連動画紹介】

研究論文を効率的に書くコツ:博士課程で学んだ実践法