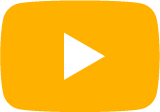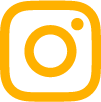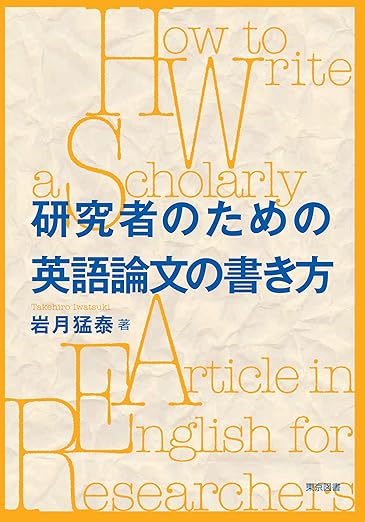研究論文を効率的に書くコツ:博士課程で学んだ実践法

論文執筆がなかなか進まずにイライラした経験はありませんか?
長い文章に迷い、書き出せないまま時間だけが過ぎる…。そんな悩みを解消するための実践的な工夫を整理しました。
まず大切なのは「上手な人を真似る」ことです。優れた論文を複数集め、段落ごとの構成を細かく分析すると共通のパターンが見えてきます。例えば序論で何段落使い、各段落にどんな要素を盛り込んでいるかを数十本規模で確認すれば、自分の論文にも応用できます。完全にコピーするのではなく、ストーリーの組み立て方を学ぶ意識が重要です。
二つ目は「文章を短く書く」こと。英語でも日本語でも、長文は理解を妨げます。特に研究論文では、余計な修飾を省き、必要最小限の要素で簡潔にまとめることで読み手に伝わりやすくなります。
三つ目は「論文の読み方を学ぶ」ことです。単に情報を拾うのではなく、著者がどのように構成を組み立てているかを意識して読むと、書く力も自然と養われます。研究目的を確認する時の読み方、方法論を吸収する時の読み方など、複数の視点を持つことが執筆力につながります。
四つ目は「目的を一つに絞る」ことです。研究であれもこれも扱おうとすると、文章が散漫になりがちです。論文では一つの明確な目的に集中し、その目的を裏付けるデータと議論に絞り込むことで、全体の一貫性が保たれます。
五つ目は「人とタッグを組む」こと。研究には得意不得意があります。序論や方法を書くのが得意な人もいれば、結果の解釈や考察に強い人もいます。共同研究で役割を分担することで、自分一人では苦手な部分を補い合い、完成度を高められます。実際、ある研究者は序論から方法までを担当し、共同研究者が結果と考察を執筆する形で効率よく論文を完成させています。
六つ目は「長い時間を確保する」ことです。論文執筆は短時間では集中が途切れやすく、生産性が落ちます。1時間を3回に分けるより、3時間をまとめて確保した方が集中状態に入りやすく、書くペースが加速します。特にアイデアが温まるにはある程度の時間が必要なため、まとまった執筆時間を意識して確保するのがおすすめです。
これらの工夫を積み重ねれば、「書けない」という悩みは確実に減ります。真似る、短く書く、読み方を学ぶ、目的を絞る、共同研究を活用する、そして長時間を確保する。この流れを実践することで、論文執筆の効率は格段に高まります。
論文執筆は才能ではなく工夫の積み重ねで進みます。構成の分析や時間管理といった具体的な方法を取り入れれば、書くスピードも精度も確実に上がります。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]
【関連動画紹介】

大学院留学の誤解を徹底解説:諦める前に知ってほしいこと