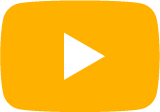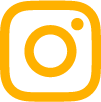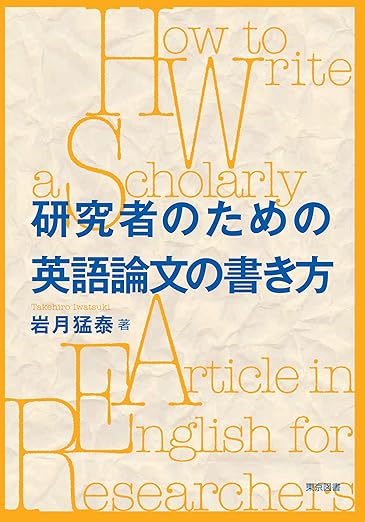論文は全部読む必要なし。目的別・効率的な研究論文読み方

論文って最初から最後まで読まないとダメ?研究や課題のために論文を読む機会が増えてくると、こう感じる人も多いのではないでしょうか?
実は、目的に応じて「読むべき場所」は大きく変わります。
論文を読むとき、まず最初に「なぜ読むのか」を明確にしておくことが大切です。例えば、論文の概要だけ知りたいなら、アブストラクト(要約)だけで十分です。研究のアイデアを探したい場合は、序論の最後あたりに目を通しましょう。
過去の研究背景をざっくり知りたいなら、序論の冒頭数段落を読めば流れがつかめます。研究の構成そのものを把握したいときは、方法論や考察に注目します。ただし、論文によって構成がやや異なる場合もあるため、複数読んでパターンをつかむことが重要です。
私は、過去に100本ほどの論文を読み込んで構成を分析し、自分なりの書き方を確立しました。こうした経験を積むことで、どのパートが自分の研究にとって重要か判断できるようになります。
研究の目的を知りたいときは、要約の冒頭や序論の終盤に書かれていることが多いです。また、英語の表現を学びたい場合も、目的を述べる部分はテンプレートとして参考になります。さらに、研究のデザインを考えるときは、方法セクションを確認しましょう。
被験者数が気になる場合は、似た研究の方法論を見て、平均的なサンプルサイズを把握することも可能です。統計手法については、結果セクションの最後あたりに記載されているケースが多く、t検定や分散分析など、使われている分析手法を確認できます。
特定の研究分野でどんな研究が行われているか知りたいときは、序論の序盤に記述があります。グラフや表の正しい作り方も、結果セクションを参考にすれば学べます。なお、表はタイトルが上に、グラフは下に記載されているのが一般的です。
論文の整え方については、APAなどのフォーマットがよく使われています。参考文献や引用の書き方も含めて、公式ガイドラインに従うのが基本です。
結果の意味がわからないときは、考察セクションを読みましょう。なぜその結果が出たのか、他の研究とどう関係しているかが解説されています。最後に、その論文で使われた参考文献を見れば、関連研究へのアクセスもしやすくなります。
研究論文は目的に応じて、読むべき場所が大きく異なります。全部を精読しなくても、必要な情報を効率よく得る方法を知っておけば、時間も労力も大きく節約できます。自分に合った読み方を見つけて、論文をもっと味方につけていきましょう。
さらに詳しく回答した動画も以下に残しておきますので、参考にされて下さいね!
【留学攻略ガイド】
もっと詳しい留学準備や学費免除の方法はLINE限定でプレゼントをしています。
👉登録はこちらから👉 [LINEリンク]

海外で研究職に就くために必要な5つの力とは。実例で学ぶキャリア戦略